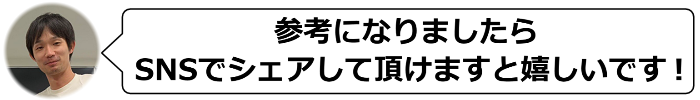【中学生でも分かる】5W1Hの意味とは?使い方と、6つの要素の正しい順番を例文で解説します
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
コミュニケーションにおいて大切なことは「相手に分かりやすく伝えること」ですが、その基本とも言えるのが「5W1H」の考え方。
5W1Hは「日常会話」や「職場での上司との会話」に活かせられるのはもちろんのこと、ビジネスにおける「マーケティング」にも使用される思考方法です。
そんな「5W1Hの考え方」について、
- どのような意味があるのか?
- どのような順番で表現・使用するべきか?
- どのようにビジネスに活かせられるのか?
- 「5W2H」や「7W2H」とはどのように違うのか?
などを、例文とともに分かりやすくまとめてみました。

5W1Hの思考を無意識に使えるようになると、ビジネス・日常会話に関わらずコミュニケーションがスムーズになりますよ。
5W1Hとは?なぜ必要なのか?
5W1Hとは、以下の6つの要素をひと言で表したものです。
- When「いつ(時間)」
- Where「どこで(場所)」
- Who「だれが(主体)」
- What「なにを(目的・人・モノ)」
- Why「なぜ(理由)」
- How「どのように(手段・方法)
このほかにも「5W2H」や「7W2H」などもありますが、もっとも一般的な考え方が「5W1H」なので、とりあえずはこれを押さえておけばOK。
※「5W2H」「7W2H」についてはページ最後で解説しています
なぜ5W1Hが必要なの?
ではなぜこの「5W1H」が大切なのか?
それは「話」「文章」に関わらず、5W1Hを押さえておくだけで物事を明確に具体化して伝えられるようになるからです。
極端な例えを出すと、
- Aさん:『あとであれもお願いねー!』
- Bさん:『えっ?あれって何ですか?』
こんな会話をしたことが一度はあるハズです。
この時、もしもBさんが「あれ」に対する確認をせずに、二人の間で「あれ」への認識が違えば、
- Bさん:『先ほどの件、やっておきました!』
- Aさん:『いやいや、これじゃないよー』
- Bさん:『え!?てっきりこれのことかと思いました…。すみません』
このような「不毛なやりとり」と「労力・時間の浪費」に繋がります。
上の例は極論ですが、『君の話(文章)はいつも分かりにくいんだよ…』と言われがちな方は、5W1Hを意識するだけで情報を分かりやすく誤解なく伝えられるようになります。
5W1Hに含まれる6つの要素(意味)を知ろう
5W1Hは「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように」の6要素であると説明しました。
- When「いつ(時間)」
- Where「どこで(場所)」
- Who「だれが(主体)」
- What「なにを(目的・人・モノ)」
- Why「なぜ(理由)」
- How「どのように(手段・方法)
ここでは、これら6つの要素を一つずつカンタンに説明します。
1.When「いつ(時間)」
Whenは【時間】を表す要素であり、日時・期限・タイミングなどが当てはまります。
- いつ(例:明日)
- いつからいつまで(例:5日から10日まで)
- タイミング(例:次に会った時に)
たとえば会話の中で「時間」の話がなければ、『期限は無いんだな』と捉えられる可能性があります。
もちろん出来る人は『で、その資料はいつまでに出せば良いの?』といった質問を返してくるハズ。
2.Where「どこで(場所)」
Whereは【どこで】を表す要素であり、場所・環境・空間などが当てはまります。
- どこで(例:事務所の会議室で)
- どんなところで(例:人が少ない場所で)
Whereでは、「それを行う場所」「待ち合わせ場所」「訪問先」などを伝えます。
場所が分かることで「目的地までの移動時間・移動手段」をイメージ出来たり、たとえばイベントをする時は「現場でのイメージ」が浮かびやすくなります。
3.Who「だれが(主体)」
Whoは【だれが】を表す要素であり、人物や企業など、主体的に行動を起こすモノを示します。
- だれが(例:担当者が)
- どんな人が(例:50歳くらいの中肉中背の人が)
Whoは「主語」を表す言葉ですが、会話や文章において抜けてしまう人が多いです。
たとえばドラッグストアで薬剤師に『喉が痛いみたいで、オススメの薬はありませんか?』と聞いたとしたら、薬剤師はきっと『大人の方ですか?子どもですか?』と聞き返すでしょう。
喉を痛がっているのが子どもなのに、「子どもに使えない薬」をオススメされても困りますよね。
このように「誰なのか」が明確にならなければ、会話が正しく(あるべき方向へ)進められないことも多々あります。
4.What「なにを(目的・人・モノ)」
Whatは【なにを】を表す要素。
- なにを(例:昨日まとめたアンケート資料を)
会話において、このWhatが抜けてしまう事もしばしば。
または「あれ/これ/それ/あの」などの言葉に置き換え、対象が曖昧になることも多々あります。
『明日までにヨロシクね!』『あれやっといてねー!』など、対象が明確になっていない会話は仕事においてミスに繋がる原因。
会話でも文章でも『察してくれるだろう』と考えるのではなく、「伝える」ための気遣いが必要です。
5.Why「なぜ(理由)」
Whyは【なぜ】を表す要素。
- なぜ(例:熱が出たため)
会社で上司に『今日は早退しても良いですか?』と聞くと、確実に『なんで?』と返されますよね。そういうことです。
また、何かを報告する場でも必ずWhyは入れておくべきです。
たとえば、私がデザイナーに『UNCHI株式会社のイメージをデザインして下さい』と依頼した場合に、『出来ました!』とデザインを見せられただけでは、良し悪しの判断が難しいです。
※UNCHI株式会社とは、筆者が運営している会社です
ですが『社長の●●という信念をこの2つの要素に落とし込んでイメージしました』と言われたら…
『おぉなるほど!このデザインにはそういう意味が込められてるのか!』と理解でき、それも私の判断材料の一つになります。
このように常に「理由」とともに報告してくれる方の場合、こちらから『なんでそうしたの?』といちいち聞き返す必要もないので楽です。
6.How「どのように(手段・方法)
Howは【どのように】を表す要素であり、具体的な手段・方法を示します。
- 手段(例:電車を使って)
- 方法(例:SNSを使って)
『電車を使って会社に行きます』『イベントの告知はTwitterやInstagramを使って行う予定です』など、「どのようにするのか」を表します。
また、たとえばあなたが「ビラを誰かに配って!」と依頼された時に、その「手段」が気になるハズです。
『道端で配るの?ポストに入れていいの?どこかのお店に置いてもらってもいいの?ポケットティッシュに入れて、ポケットティッシュを配る方法でもいいの?』などなど…。
Howが抜けていると、聞き手からすれば『結局(私は)どうすればいいの?』『(あなたは)どのようにするつもりなの?』という疑問が残ってしまいます。
5W1Hの「正しい順番」を例文とともに解説
6つの要素が理解できたと思いますので、ここからは5W1Hの「正しい順番」を例文とともに紹介します。
まず、5W1Hの基本的な順番としては以下の通りです。
- いつ(When)
- どこで(Where)
- だれが(Who)
- なにを(What)
- なんのために(Why)
- どのように(How)
では、この基本的な順番に当てた会話例を挙げてみます。
- When:13日午後3時から
- Where:本社2階会議室Bにて、
- Who:技術者チームが
- What:新たなシステムを発表します。
- Why:営業の方に「実際の使い勝手」を知ってらもらえるように
- How:デモ機を用いた説明をします。
場合によっては順番は入れ替えるべき!
上記の例は、もっとも一般的な順序での組み立て方ですが、必ずしもこの通りに組み立てる必要はありません。
- Whyから始める
⇒目的や、その経緯を理解してもらう場合
- Whoから始める
⇒その事柄に関わっている人物が重要な場合
たとえば…
13日午後3時から本社2階会議室Bにて、技術者チームが新たなシステムを発表します。営業の方に「実際の使い勝手」を知ってらもらえるようにデモ機を用いた説明をします。
という説明よりも、以下の順番の方が自然に感じる方もいらっしゃると思います。
- 技術者チームが新システムを発表しますので、13日午後3時から本社2階会議室Bにお集まりください。その際、営業の方へ「実際の使い勝手」を知ってらもらえるように、デモ機を用いた説明をします。
- 技術者チームが新システムを発表します。その際、営業の方へ「実際の使い勝手」を知ってらもらえるように、デモ機を用いた説明をします。13日午後3時から本社2階会議室Bにお集まりください。
これは最初に「日時」「場所」を言われても、当事者意識がなければ耳に入らないからです。

5W1Hに絶対的な順番はありません。
あくまでも「6つの要素が入っていれば具体的に伝わりやすい」という考え方なので、必要に応じて順番は入れ替えましょう。
ビジネス・マーケティングにも利用できる!
5W1Hの考え方は「商品開発」や「ブランドコンセプト作り」といった、ビジネス・マーケティングの世界でも使えます。
商品開発やコンセプト作りに応用する場合
商品開発やコンセプト作りに応用する場合は、まずは「Why(何のために)」「Whom(誰のために)」から考えると良いです。
※「Whom」は後ほど説明します
ビジネスの基本は「需要」に対して「供給」していくことなので、まずは【需要】を見定めることが大切。
一方で「What(どんなものを作るか)」からスタートしてしまうと、
- すでに世の中にあるものと似たようなもの(差別化出来てないもの)
- 需要がないもの
を作ってしまう可能性があります。
「需要がないもの」について極端な例を挙げると、高齢者が多い島で「脂ギットリの二郎系ラーメン屋」を出すようなものです。
そのような間違った判断をしないためにも、
- Why:学生の多い街にも関わらず、あっさりしたラーメン屋しかないため
- Whom:お金のない食べ盛りの若い学生のために
- Where:駅から大学への通学路に
- What:安くてお腹がいっぱいになり、スタミナもつく二郎系ラーメンを…
という思考の流れが望ましいです。
あまり難しく考える必要は無く、とりあえずは起点を「Why(何のため)」「Whom(誰のため)」とすればOK。
その後は特に順番に固執することなくWhere・When・What・Howを考えていけば良いです。
なお「Whom」については、後ほど 7W2Hとは? で説明します。
関連ページ
>>コンセプトの意味とは?なぜ必要?例とともに分かりやすく解説
問題解決に応用する場合
5W1Hは問題が起きたときの解決にも利用できます。
多くの場合、問題が起きた時に真っ先に「Why(なぜ)」を突き止めようとします。
しかし状況を整理するためには、先に他の要素を洗い出した方が「トラブルの本質」に気づきやすくなります。
まずは以下を洗い出す…
- What:何が原因となり、どのような問題が起きているのか?
- When:いつ起きたのか?いまも起きているのか?
- Where:どこで、どのような状況で起きているのか?
- Who:誰が関わっているのか?
そのあとに…
- Why:なぜその問題が起きているのか?
- How:どのように解決できるのか?
このように「Why」意外を整理することで、「Why(なぜ)」だけでは見えずらい原因までもを分析できます。

ビジネス・日常に関わらず、「5W1H」の思考で整理できるケースは多々ありますね。
5W1Hのメリット・デメリット!
5W1Hを使うことによるメリット・デメリットを簡単にまとめてみました。
「5W1H」を使うメリット
- 5W1Hの構成に当てはめることで、「情報の過不足」に気づける
- つまり相手に正しく情報が伝わることで、認識のズレが発生しにくく(手戻りが発生しにくい)、お互い無駄な時間・労力を費やさない
- もちろん議事録など「あとで他人が読み返すもの」についても、担当者以外の人間に内容が明確に伝わる
「5W1H」を使うデメリット
- 会話が冗長になりやすく、日常会話で多様すると「説明くさい人」になってしまう
⇒関係性に応じて、不要な情報は省略した方が良い
「5W2H」「7W2H」との違いは?
では最後に、「5W2H」や「7W2H」についても触れておきます。
5W2Hとは?
「5W2H」は「5W1H」に【How much】を加えたもの。
How muchは「いくらで?」を示すものであり、たとえば『100万円の予算を使って…』のように、会話における「コスト」についての要素です。
なお、人によってはこの付け加えられた「H」を【How many】とする方もいらっしゃいます。
How manyは「どのくらいの数で?」を示すものであり、たとえば『週に5日の頻度で…』や『50トン分限定で…』など定量的な要素と言えます。
この「How much」と「How many」を含めて【5W3H】とする人もいますが、そのあたりの細かい取り決めはありませんので、「思考に必要な要素」を自由に取り込めば良いでしょう。
7W2Hとは?
「7W2H」は、上記の「5W2H」に【Which:どちら】【Whom:だれに】の2要素を付け加えたものです。
- Which:どちらから
⇒優先順位を決めるもの
- Whom:だれに
⇒ビジネス・マーケティングにおいてのターゲット像
「Which」は分かりにくいと思いますが、たとえば飲食店のメニューにおいて『どのメニューをイチオシとして売り出すのか』などを決めます。
「Whom」はシンプルに『誰にそのサービスを提供するのか』を決めるものであり、ビジネスに用いる時には欠かせない要素です。
まとめ
5W1Hの意味や使い方、順番の考え方や、ビジネスへの応用について解説しました。
さいごに、当ページの内容を簡単にまとめておきます。
- 5W1Hは「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように」をまとめたもの
- 5W1Hを意識すると、物事を明確に具体的に伝えられるようになる
- この6要素の一般的な順序は「いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのように」と言われているが、絶対的な決まりは無く、「なぜ」から始める方が良い場合もある
- ビジネスにおいては「Why(何のため)」「Whom(誰のため)」を起点として考えると、顧客目線に立てやすくなる
- 5W2Hでは「How much(いくら)」「How many(どれくらい)」など、「量・コスト」を示す要素が加わる
- 7W2Hでは「Which(どちら)」「Whom(誰のために)」が加わる
以上、参考になりましたら幸いです。
関連ページ
>>コンセプトの意味とは?なぜ必要?例とともに分かりやすく解説