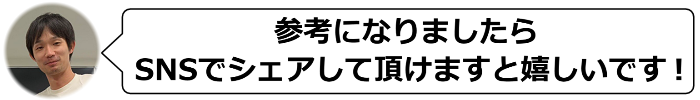コンセンサスの意味とは?5つの使い方を解説【中学生でも分かる】
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
ビジネスの世界では、「コンセンサス」という言葉がたびたび使われます。
しかし『何となく使ってるけど、いまいち理解していない』という方が多いと思います。
そこでこのページでは、「コンセンサス」の使い方や注意点などを【超わかりやすく】まとめました。

コンセンサスは、使われる場面によって微妙にニュアンスが異なります。
しっかりと違いを理解しておきましょう!
ビジネスシーンでの2つの意味・使い方!
コンセンサスとは、英単語「consensus」をカタカナ読みした言葉であり、英単語として以下の様な意味があります。
- (全体の)ほぼ一致した意見
- 総意
- 意見の一致
まずは日本のビジネスシーンにおける「コンセンサス」の使い方を、2通り解説します。
ビジネスシーンにおける2通りの意味①「複数人での合意」「意見の一致」という意味
1つ目の使い方としては、英単語の意味そのままに、「複数人での合意」「意見の一致」という意味で使われます。
ただし冒頭で紹介した意味の一つである「(全体の)ほぼ一致した意見」というニュアンスではなく、「全員の一致」「全員に合意を取る」という意味で使われることがほとんど。
「コンセンサス方式」が分かりやすい例
会議の進め方の一つに「コンセンサス方式」があります。
これは多数決のような「一部に反対意見があっても進める」というものではなく、「全会一致で結論を導き出す方法」です。
多数決では必ずしも全会一致にはならないため、一部の反対意見を持つ人には不満が生まれます。
しかしコンセンサス方式では、決議が承認される時は「全員の意思が一致している(反対意見がいない)時」。
つまり不満が生まれず、その後は目標に向かいスムーズにことを運べるのです。
この「コンセンサス方式」は、まさに【全員の一致(同意)】を意味していますね。
「全員の一致」の意味での例文
- 保育園では騒音問題が発生するため、地域住民のコンセンサスを得ることが大切だ。
- 全店舗のコンセンサスを得るのは大変だから、本部の一存で決めましょう。

コンセンサスは「全員の合意」のニュアンスで使われるため、合意を得る相手が1人の場合は「アグリーメント」の方が相応しいでしょう。
ビジネスシーンにおける2通りの意味②「根回し」という意味
コンセンサスは「根回し」という意味でも使われます。
上で挙げた「コンセンサス方式での会議」では、会議の場において【全員の同意】が求められるため、会議前に意見調整をしておく必要があります。
「ことが上手く運ぶように、予め手を打っておく」ということであり、これは言い換えると「根回ししておく」ということ。
そのような意味から転じて、コンセンサスは「根回し」の意味でも使われています。
「根回し」の意味での例文
- 後々のトラブルを回避するためにも、事前に関係者のコンセンサスを取っておきなよ!
- 明日のミーティングまでに部長からのコンセンサス取っておいてね!
コンセンサスを「得る」「取る」の違いとは?
コンセンサスと一緒に使われることの多い動詞「得る・取る」について、その「違い」が気になる方もいらっしゃると思います。
この違いについて、結論から述べると以下の通りです。
- コンセンサスを「得る」の場合
【全会一致】の意味で使われることが多い
- コンセンサスを「取る」の場合
【根回し】の意味合いで使われることが多い
しかし実際は曖昧であり、あまり気にする必要は無いと考えています。
なぜなら「新語時事用語辞典」や「実用日本語表現辞典」など、辞典間であっても説明が異なっているためです。
またwebサイトによっても説明が異なっており、『厳密に使い分けている人の方が少ないのでは?』と感じます。
それよりも『全店舗のコンセンサスを取る』のような、グループ・チームなどを対象した場合は、全体の合意が必要となるため「全会一致」に近い意味となると覚えておく方が分かりやすいと、個人的には考えています。
一方で『〇〇さんのコンセンサスを取る』であれば、「根回し」のニュアンスで伝わってくるかと思います。
そのほか「3つのシーン」での使われ方!
コンセンサスを使った3つの用語を紹介します。
コンセンサスを使った3つの用語①コンセンサスレーティング(予想)
コンセンサス・レーティングとは、株式取引において「複数の証券アナリストたちの共通認識」という意味で使われます。
また「複数アナリストによる、とある会社の業績予想を平均化したもの」をコンセンサス予想と言います。
(これ自体をコンセンサスレーティングという場合もあります)
コンセンサスを使った3つの用語②コンセンサスゲーム
コンセンサスゲームとは、与えられる課題に対しチームで話し合い、コンセンサス(全体での合意)を目指すゲームのこと。
チームにおける合意形成(全体合意までのステップ)の難しさを肌で体感することを目的としており、ビジネス研修・チームビルディングのグループワークなどで利用されています。
コンセンサスを使った3つの用語③コンセンサスアルゴリズム
「コンセンサスアルゴリズム」とは、仮想通貨業界で使われている「データが正しいことを担保するルール」のこと。
たとえばビットコインのような非中央集権型の仮想通貨では、世界中のマイナーにより「同じトランザクション」に対して計算・記録処理が行われています。
しかし計算ミスやデータ改ざんなどが含まれ、マイナー間で「処理結果」が異なる場合があります。
その場合に『どのマイナーの計算結果が正しいのか?』を決めるルールのことを、「コンセンサスアルゴリズム」と言います。
コンセンサスの語源とは?
コンセンスはラテン語の「consentire」がもともとの語源。
これは「con」+「sentire」から成り立った言葉であり、それぞれ以下の意味があります。
- con
⇒withやtogetherのような「一緒に」と同じ
- sentire
⇒feelやsenseのような「感じる」と同じ
つまり「共に感じる」から転じて「全体の合意」という意味で使われています。
ちなみに「consensus」に限らず、ラテン語が語源となっている英単語はたくさんありますね。
▼「consensus」の発音▼
まとめ
コンセンサスの意味や使い方などを解説しました。
最後に簡単にまとめておきます。
- コンセンサスは英単語「consensus」をカタカナ読みした言葉
- ビジネスシーンの使われ方の一つが「全員の一致」「全員に合意を取る」という意味合い
- 「全員の意見が合致するように、予め調整しておく(つまり根回しのこと)」という意味でも使われる
- コンセンサスを「得る・取る」の使い分けについては、曖昧な部分が多いため、コンセンサスを取る(得る)対象が「複数なのか」「個人なのか」でわけて考えた方が分かりやすい(複数=全員の一致、個人=根回し)
- コンセンスはラテン語の「consentire」が語源