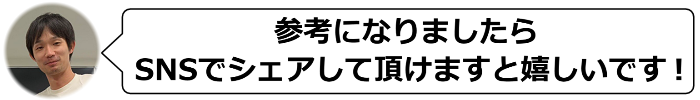【10秒でわかる】レギュレーションとは?「意味」と「7つの使い方」をわかりやすく解説
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
ビジネスの世界で使われることの多い「レギュレーション」という言葉。
ここでは【中学生でも分かる】を目標に、「レギュレーション」の意味・業界ごとの使い方・類語との違いなどを分かりやすく解説します。

難しい言葉ではありませんが、使われる業界によってニュアンスが異なりますのでしっかりと意味を理解しましょう。
レギュレーションの意味とは?まずは10秒で理解!
結論から述べますと、レギュレーション(regulation)とは「絶対に守らなければならない決まり事や禁止事項」のことです。
この『絶対に守らなければならない』とはどのくらいの程度なのかというと、
- 違反すると罪に問われる
- 違反すると懲戒処分(減給や降格など)などの対象となりうる
- 違反すると社会的に立場が悪くなる可能性がある
このように、「(場合によっては法令並みに)強く守るべき決まり事」に対してレギュレーションと呼びます。
なおレギュレーションに違反した場合に、「罪に問われる」「何らかの処分がある」「罰則までは無い」という【程度】は、使われる業界で変わります。
この辺りは後ほど「各業界における使い方」で説明します。

基本的には「法令的な意味合いは含まないが、強く守るべき決まり事」というニュアンスで使われていると考えておけばOK。
「ルール」との違いを例文で解説します
レギュレーションと似た意味を持つ言葉が「ルール(rule)」です。
両方とも「守らなければならない決まり事や禁止事項」という意味があります。
しかし、「ルール」には『法令並みに強く守るべき』というほどの意味合いを持ちません。
「ルール」の程度を表す例を出してみましょう。
【例】田中家には門限8時というルールがある
上の例において、長女が門限を30分破ったとして、罪に問われたり、懲戒処分を受けたりすることはないですよね。
両親に叱られるくらいであり、これは「田中家のルール」です。

一方の「レギュレーション」はより守らなければならないもので、より厳格なイメージです。
「コンプライアンス」との違いは?
コンプライアンス(compliance)とは、直訳すると、「法令遵守(順守)」。
カンタンに言うと『決まりを守ること』です。
レギュレーションは、「規則」「規定」など『決まりそのもの』のことを指します。
「レギュレーション」の7つの使い方を解説
レギュレーションは、業界や分野によってニュアンスが異なるため、相手に合わせた使い分けが大切です。
ここでは、各分野における「レギュレーション」の使われ方をまとめてみました。
「レギュレーション」の7つの使い方①「ビジネスシーン」での使われ方
一般的に、ビジネスシーンにおける「レギュレーション」とは、「社内規定」や「就業規則」のことを指します。
【使用例】
申告せずに副業することは、わが社のレギュレーションに違反しています。
また他にも、以下のように使われます。
外注する時の「レギュレーション」
この場合の意味合いとしては、「外注する際に、誰が受注しても質を保てるよう細かい決まり事を定めること」です。
【使用例】
出汁とタレは、このレギュレーションに従って「仕込み」「納品」してください。
レギュレーションシート
レギュレーションシートとは、レギュレーション内容をまとめた用紙のこと。
たとえば、会社のロゴのコンセプトや、使用している色などが記載されている「ロゴレギュレーションシート」というものがあります。
これ利用することで、どの業者が受注してもロゴのブランドイメージを守りながら、名刺やパンフレットなど様々なシーンでロゴを活用できます。
「レギュレーション」の7つの使い方②「IT業界」での使われ方
IT業界における「レギュレーション」とは、WEB制作や広告制作にあたっての「細かな仕様や方針」のことを指します。
具体的には、以下の様な細かな条件を指します。
- 表現方法
- 禁止ワード
- データ量
- ロゴやバナーの色
これらは「ブランドイメージを守ること」や「WEBサイトにおける品質の管理」を目的に定められています。
【使用例】
- ブランドイメージを壊さないためにも、レギュレーションを守って広告制作してください。
- 不具合を調査したところ、一部レギュレーションが守られていなかった。

IT業界では「品質管理のための仕様・方針」のニュアンスが強いため、「IT業界」というくくりにしました。
しかし言い換えれば「品質管理のための規則」とも言えますので、①ビジネスシーンでの使われ方と大差はないですね。
「レギュレーション」の7つの使い方③「ゲーム業界」での使われ方
ゲーム業界の「レギュレーション」とは、「ゲームの遊び方」や「施設の使い方」のことを指します。
「ルール」と表現されることもありますが、参加人数を多い場合や、より競技として成り立たせたい場合に「レギュレーション」と表現されます。
つまり、以下の通り使い分けられています。
- 家庭で楽しむような場合は「ルール」
- 参加者が多い大会では「レギュレーション」
関連して「レギュレーションマーク」とは、「レギュレーション」が定められた大きな大会で、使用して良いカードに記載されたマークのこと。
主に、ポケットモンスターシリーズのカードゲーム(通称ポケカ)で用いられます。
詳しくはGoogle等でお調べ下さい。
「レギュレーション」の7つの使い方④「建築業界」での使われ方
建築業界のレギュレーションは、「建築設計を行う際の基準や規定」のこと。
具体的には、
- 耐震や免震に対する安全基準
- 建物の高さ・色制限などの規定
などを指します。
建築基準法の一部を「レギュレーション」として表現することもあり、レギュレーション違反では「罰則」があります。
このように建築業界においては、一般的にビジネスで使われるレギュレーションとは違い、「法令的な意味合い」が含まれます。
「レギュレーション」の7つの使い方⑤「F1業界」での使われ方
F1業界のレギュレーションとは、「レースをするための規定」のことです。
世界選手権では、「スポーティング・レギュレーション」と「テクニカル・レギュレーション」があります。
- スポーティング・レギュレーション
⇒レース内容などの競技の規約のこと。
- テクニカル・レギュレーション
⇒たとえば「使用してよいエンジンの種類」など、マシンに関する規約のこと。

なおF1界におけるレギュレーションは、技術の進化とともに変わるため、その度にファンの間で大きな話題となります。
「レギュレーション」の7つの使い方⑥「スポーツ業界」での使われ方
スポーツ業界のレギュレーションとは、「競技運営のための規定・規則のこと」です。
なお「ルール」は、競技そのものの規則を指します。
たとえば、オリンピックにおける参加資格として『ドーピングをしていないこと』は「レギュレーション」。
一方で『サッカー選手は、キーパー以外ボールを手で触ってはいけない』という決まりは、「ルール」です。
「レギュレーション」の7つの使い方⑦「医療業界」での使われ方
医療業界のレギュレーションとは、医薬品や医療機器に対する厳格な規則のことを指します。
品質・有効性・安全性を確保するために、とても厳しく定められています。
たとえば、新薬を開発する場合の評価方法や評価基準が「レギュレーション」です。

その他、医療業界においては「アップレギュレーション」「ダウンレギュレーション」という言葉も使われますが、医療に関する詳しい説明は専門外のため割愛します。
『レギュレーションをとる』は正しい使い方か?
Googleで「レギュレーション」と調べると、『レギュレーションをとる』という言葉が出てきます。
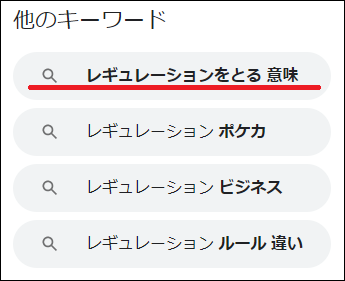
では、この使い方は正しいのか?
結論から言うと、『辞書には載っていない使い方(表現)であり、正しいとは言えないと思うが、共通認識を持って皆が使っている』と言えます。
※「辞書に載っている=正しい」「辞書に載っていない=正しくない」という前提のもとです
この『レギュレーションをとる』という表現は、主に2つのニュアンス(意味)で使われています。
「レギュレーションをとる」の使われ方①決まりとする・決まりをつくる
1つ目の使われ方としては、「決まりとする」「決まりをつくる」というニュアンスです。
【使用例】
業務委託において細かいレギュレーションをとることは、品質維持において重要なことである。
「レギュレーションをとる」の使われ方②決まりに従う(決まりに則る)
2つ目の使われ方としては、「決まりに従う(則る)」というニュアンスです。
【使用例】
全スポーツ選手がレギュレーションをとることで、公平な試合となる。
レギュレーションの類語と、カンタンな説明
レギュレーションの類語としては、以下のようなものがあります。
- 決まり
- 規則
⇒従うべき決まり。それに基づいて、手続きや操作が行われるように定めたもの。
- 規制
⇒従うべき決まり。規則に従って制限すること。
- 規格
⇒寸法や形などについて定めた標準のこと。
- 規程
⇒行政や組織の内部での、事務手続きなどについて定めたもの。
- 規準
⇒模範・標準となるもの。従うべき決まり。
- 条例
⇒地方公共団体が定める、その区域内で適用される法のこと。
- 法令
⇒公的な掟のこと。「法律」や「命令」「条例」を含んだ言葉。
レギュレーションの反対の言葉(対義語)とは?
レギュレーションの反対の言葉は「deregulation」。
日本においてはカタカナ読みで、
- ディレグレーション
- デレグレーション
の両方が使われます。
deregulationには、「規制緩和」「規制撤廃」「自由化」などの意味があります。
【使用例】
イギリスでは、マスク着用義務などに対してディレギュレーションを進めている。
まとめ
レギュレーションの意味や使い方、似た言葉との違いについて解説しました。
最後にカンタンにまとめます。
- レギュレーションとは「絶対に守らなければならない決まり事や禁止事項」のこと
- 一般的にビジネスシーンで使われるが、業界によって「法令」レベルなのか、「規則・規約」レベルなのかが変わる
- 似た言葉に「ルール」があるが、これは『法令並みに強く守るべき』というほどの意味合いを持たない
- コンプライアンスは『決まりを守ること』であり、レギュレーションは『決まりそのもの』のこと
- ビジネスシーンによって、「社内規定・就業規則」「質を担保するための細かな決まり」「ゲームの遊び方」「競技運営の規定」など様々
- 建築業界においては「法令的な意味合い」が含まれるが、一般的には「絶対に守るべきこと」というニュアンス