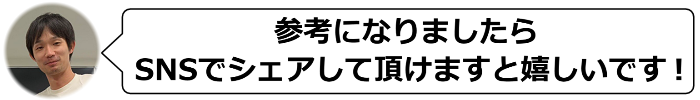7割が知らない「了解しました/承知しました」の違いと、正しい敬語の使い方!
「承知いたしました」については、以下のページをご覧ください。
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
ビジネスにおいて多くの方とやり取りする中で、「了解」「承知」という言葉が飛び交います。
しかしこの2つの言葉を「使い分けてる人」もいれば、「全く気にしていないであろう人」も大勢いらっしゃいます。
この記事では、そんな「了解」「承知」について
- 「了解しました」と「承知しました」は何が違い、どう使い分けるべきか?
- これらの言葉は「敬語」ではどのように表現するのか?
- 「了解いたしました」は、目上に対して失礼な表現になるのか?
- 「了解です」「承知です」という表現は正しいのか?
- どのような「言い換え」表現があるのか?
などの問いへお答えしていきます。
ちなみに今回、100人に対して『2つの違いが分かりますか?』とアンケートをとったところ、7割の方は明確には理解できていませんでした。
相手から「非常識な人だ」と思われてしまわないよう、正しい使い分けを覚えましょう。

ビジネスの場では、特に気を付けて使い分けましょう!
まずは結論から!「了解しました」と「承知しました」の使い分け
「了解しました」と「承知しました」は、カンタンに言えば「わかりました」という意味の言葉。
2つの言葉の使い分けについて、結論から述べると
- 同僚や目下の人に使う場合は「了解しました」
- 目上の人に使う場合は「承知しました」
が正解です。

「例文」で使い分けのイメージを掴もう!
カンタンに理解できるよう、例文を挙げてみましょう。
■自分
『来週のミーティングの会議室、いつもの場所が取れなかったので隣の第2会議室に変更になります。』
■上司
『了解です。念のため、前日にも皆さんへアナウンスしてもらえますか。』
■自分
『承知しました。』

上の例では「了解です」という表現を使いました。
しかし、たとえ「了解しました」という丁寧な表現であっても、目上の方に使うことは適切ではありません。
その理由はこのあと解説します。
7割が知らない「了解/承知」の本当の意味と違い
同じ「分かりました」という意味ですが、字の意味を細かく見ることで、ニュアンスの違いを理解できます。
「了解」「承知」のニュアンスの違い①「了解」という字の意味
まずは「了解」について。
「了」と「解」、それぞれの漢字が持つ意味は以下の通りです。
- 「了」
⇒もっともだと認める
- 「解」
⇒分かる
たとえば、部長からの指示に対して、新人が『了解しました』と言った場合。
これは「部長の指示は理解できたし、もっともだと認めました」というニュアンスになります。
「誰が誰に言ってるんだ」感がありますよね。
このことからビジネスマナーとして、「了解」という言葉は目上の人に対して使いません。
「了解」「承知」のニュアンスの違い②「承知」という字の意味
続いて「承知」について。
「承」と「知」、それぞれの漢字が持つ意味は以下の通りです。
- 「承」
⇒相手の意向を受け入れる
- 「知」
⇒物事の本質を知る
たとえば、部長からの指示に対して、新人が『承知しました』と言った場合。
これは「部長の指示を深く理解し、私も同じ想いで対応します」というニュアンスになります。
「指示への理解の深さ」や「相手への尊敬の念」を感じることができますよね。
このことから、「承知」という言葉は取引先や目上の人へ使われます。
7割の方が「明確な使い分け方」を知らない
余談ではありますが、【了解と承知の明確な違いを知っているか】についてWeb上で100人に質問したところ、7割の方が「知らない」もしくは「間違っている」という結果に。


「7割の方が知らない・間違っている」とは言え、8割の方が「(“何となく” も含め)使い分けている」という事実が分かりますね。
「了解しました / 承知しました」の敬語表現まとめ!
敬語とは「丁寧語・尊敬語・謙譲語」の3つを指します。
「了解しました」と「承知しました」は、「了解した」と「承知した」の丁寧語ですから、敬語の一種ではあります。
以下に、丁寧語・尊敬語・謙譲語をまとめました。

なお、敬語とは以下の通りです。
「敬語」は3種類ある①丁寧語
丁寧語とは、相手に対する言い方を丁寧にする言葉です。
【例】
- 私がします(「する」の丁寧語)
- ここにいます(「いる」の丁寧語)
「敬語」は3種類ある②謙譲語
謙譲語とは、自分がへりくだることで相手へ敬う気持ちを表現する言葉です。
【例】
- 来週伺います(「行く」の謙譲語)
- 先方へ参ります(「行く」の謙譲語)
- ご連絡いたしました(「する」の謙譲語)
- ご依頼いただきました(「もらう」の謙譲語)
「敬語」は3種類ある③尊敬語
尊敬語とは、相手を持ち上げることで敬う気持ちを表現する言葉です。
【例】
- 社長がいらっしゃいました(「くる」の尊敬語)
- アドバイスをくださりありがとうございます(「あげる/あたえる」の尊敬語)
- 食後のデザートを召し上がりください(「食べる」の尊敬語)
「了解いたしました」は目上に対して失礼ではない?
目上の人への「了解しました」は、適切ではないという話をさせていただきました。
では、より丁寧な言い回しの「了解いたしました」はどうなのか?
結論を言うと、【使っても問題はないが、あえて使う必要はない】です。
「敬意」はプラスされるが…
辞書を引くとわかりますが、「いたす」とは「する」の謙譲語。
謙譲語とは、「自分の動作を低めて言うことで、相手に対する敬意を表す言葉」です。
つまり、ただの丁寧語である「了解しました」に敬意がプラスされるため、目上の人に使っても問題はありません。
しかし先にも述べたように、「了解」自体の意味合いが目上の人へ使うには不適切なので、人によっては「ん?」と引っかかることも…。
不快に感じられる可能性が少しでもあるのであれば、やはり「承知しました」を使う方が無難でおすすめです。
ちなみに!8割近くが「気にしない」
【部下や後輩からの「了解いたしました」は気になるか?】について、アンケートで100人の意見を聞いてみたところ、8割近くは「気にしない」という結果になりました。

ただし、裏を返せば2割は「気にはなっている」ということです。

アンケートではこのような結果になりましたが、そもそも相手が「了解=目上には使わない言葉」という認識を持っている場合、その相手から「非常識な人」と思われてしまう可能性は0ではありません。
結局は「相手次第」なところがありますので、無難に『承知しました』を使いましょう。
「了解です/承知です」は正しい日本語なのか?
これまで「了解しました」と「承知しました」を説明してきました。
しかし「了解」と「承知」を丁寧語にした表現には、他にも「了解です/承知です」があります。
「了解です」は違和感ないが、目上への使用は注意
まずは「了解です」について。
以下の通り、どちらでも違和感はありません。
- 後輩「この資料ここに提出しておきますね」 先輩「了解です」
- 後輩「この資料ここに提出しておきますね」 先輩「了解しました」
ただしGoogleで「了解です」と調べると、「むかつく」というキーワードが出てきます。

つまり「了解です」と言われた相手としては、一定数「むかついている人がいる」ということですから、特に目下から目上には使わない方が良いでしょう。
「承知です」は使い方に注意
「承知です」については、返答に使うと不自然に感じるので注意が必要。
- × 先輩「これ書類まとめといてくれる?」 後輩「承知です」
- ○ 先輩「これ書類まとめといてくれる?」 後輩「承知しました」
「承知です」となると、『依頼や要求を聞き入れる』意味合いよりも、『事情を知っている』という意味合いになるため、違和感が出ます。
そのため、「承知です」は以下のような使われ方をします。
【例文】
- 力量不足なのは自分も承知です。
- 社長もご承知です。
- その計画が失敗していることは承知です。
「了解しました/承知しました」の5つの言い換え
「了解しました」や「承知しました」には、似た言葉や言い換えが色々あります。
ただし、それぞれニュアンスが微妙に異なるため、時と場合に応じて使い分けが必要です。
「了解しました/承知しました」の5つの言い換え①分かりました
「分かりました」の意味は、【意味をはっきりととらえること。または、理解して受け入れること】。
「分かる」の丁寧語です。
「了解しました」と同様に、敬意の度合いは低めな言葉となります。
【例文】
(フランクな関係性で)分かりました。対応しておきますね。
関連ページ
>>「わかりました」の正しい敬語表現と、5つの言い換えを解説
「了解しました/承知しました」の5つの言い換え②理解しました
「理解しました」の意味は、【意味や意図を正しく分かること】。
単に『意味が分かる』の意で使われます。
【例文】
3回読んで、ようやくこの書籍を理解しました。
「了解しました/承知しました」の5つの言い換え③了承しました
「了承しました」の意味は、【事情をよく理解して聞き入れること】。
「了解」よりもより『相手を認める』というニュアンスが強くなり、「了解」と同じく目上の人へは使わない言葉です。
【例文】
Aさん(部下)の提案は了承しました。すぐに取り掛かってください。
「了解しました/承知しました」の5つの言い換え④かしこまりました
「かしこまりました」の意味は、【命令や依頼をつつしんで承ること】。
「承知しました」のように、目上の人や顧客に対して使う言葉です。
【例文】
お客様のご要望について、かしこましました。後日対応内容を改めてご連絡致します。
関連ページ
>>9割が知らない「承知いたしました/かしこまりました」の意味と違い
「了解しました/承知しました」の5つの言い換え⑤御意に従います
「御意に従います」の意味は、【目上の人の考えや気持ちを受け入れること】。
「承知しました」と意味合いは似ていますが、現代ではあまり使われない言葉です。
【例文】
お館さまの御意に従います。
「了解できない / 承知できない」の意味を知ると、理解が深まる!
「了解できない / 承知できない」とは、単に『分からない(理解できない)』という意味ではありません。
それぞれ以下のような意味を持ちます。
- 理解できない
⇒単に意味が分からないさま
- 了解できない
⇒意味は理解できるが、納得できないさま
- 承知できない
⇒本質は理解できるが、意向を受け入れられないさま
なおビジネスシーンで使う場合は、「○○できない」ではなく、より柔らかい表現である「○○しかねる」を使います。
【例文①】
- 『この契約の条件は理解しかねます。』
⇒「この契約条件は意味が分からない」ということ。
【例文②】
- 『この条件で契約を提案することに了解しかねます。』
⇒「この条件での提案自体は理解しているが、納得できない」ということ。
【例文③】
- 『この条件での契約に同意することは承知しかねます。』
⇒「この条件での契約自体は理解しているが、同意することは受け入れられない」ということ。
アンケート結果まとめ!
この記事をまとめるにあたって、クラウドサービスで100人に対して3つのアンケートを取りました。
ここまでの説明の中でも紹介しましたが、最後にまとめて掲載しておきます。
質問①
「了解」と「承知」の違いについて、どのような認識を持っているのか?
また、使い分けている人は「明確な根拠」を知った上で使い分けているのか?

質問②
部下や後輩からの「了解しました」は気になるか?

質問③
部下や後輩からの「了解いたしました」は気になるか?


設問②と③の違いは、「了解しました」か「了解いたしました」の微妙な違いです。
しかしこれだけの違いでも、「気になる」方の数が結構変わることが分かりますね。
目上の方には「承知しました」が無難ですが、どうしても「了解」を使いたいのであれば、「了解いたしました」を使いましょう。
まとめ
「了解しました」と「承知しました」の違いについて解説しました。
最後にカンタンにまとめておきます。
- 「了解しました」と「承知しました」は、カンタンに言えば「わかりました」という意味の言葉
- 同僚や目下の人に使う場合は「了解しました」を使う
- 目上の人に使う場合は「承知しました」を使う
- 「了解」という文字は、『あなたの言うことは理解できたし、もっともだと認めました』というニュアンスがあり、目上にはふさわしくない
- 「承知」という文字は、『物事を深く理解し、相手の意向を受け入れます』というニュアンスがあり、目上にも使える言葉である
- 了解の丁寧語は「了解しました」、謙譲語は「了解いたしました」、尊敬語は「(相手が)ご了解くださいました」。
- 承知の丁寧語は「承知しました」、謙譲語は「承知いたしました」、尊敬語は「(相手が)ご承知くださいました」。
- 「了解いたしました」は「了解しました+敬意」となるため、目上の人に使っても良い。ただし「了解」自体の意味合いが目上の人に使うには不適切なため、使わない方が無難。
- 「了解です」は自然に使えるが、「承知です」の場合は『依頼や要求を聞き入れる』意味合いよりも、『事情を知っている』という意味合いになるため、使い方に注意。