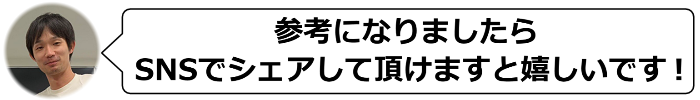トレードオフの意味とは?7つの具体例でわかりやすく解説します
こんにちは。
大阪で、行列の出来るラーメン店「人類みな麺類」など、6つのラーメンブランドを運営している松村貴大(@jinrui_mina_men)と申します。
ビジネスシーンだけでなく、日常生活でも使われることのある「トレードオフ」という言葉。
ここでは【中学生でも分かる】を目標に、「トレードオフ」の意味を具体例を用いて分かりやすく解説します。

ビジネス用語ではありますが、意味することはとてもシンプルで簡単な言葉です。
トレードオフの意味とは?まずはザックリと解説
トレーオフとは、簡単に言うと「何かを得る時には、何か別の物を失う」ということ。
四字熟語の「一得一失(いっとくいっしつ)」と同じ意味です。
たとえば、お金を得るために一日中働いた場合には、何を失うでしょうか?

答えは【時間】です。
家族と過ごす時間なのか、趣味の時間なのか、自分を磨く時間なのか、人それぞれ失うものは違うと思いますが、「お金」を得る代わりに「自由に使える時間」を犠牲にしています。
このような、「何かを得る時に何かを失う」状態をトレードオフと言います。
なぜ「trade off」なのか?語源の意味とは
トレードオフは、英語の「trade」と「off」を組み合わせた言葉。
日本語に翻訳すると?
- trade
⇒取引・貿易・商いなど
- off
⇒立ち去る・なくなる・断たれるなど
これを直訳すると「取り引きが無くなる」です。
取り引きは「売る人」と「買う人」が、お互い納得できる条件で行われます。
しかしお互いが条件を譲らない場合は、交渉が決裂して取り引きが無くなりますよね。
それはつまり、「何かを譲る(失う)ことをしなければ、何かを得ることはできない」ということであり、この状態を表す言葉として「トレードオフ」という言葉が使われるようになりました。
日常生活にあるトレードオフの3つの例
上で挙げた「労働収入と時間」も日常生活におけるトレードオフと言えますが、ほかにも日常生活における3つの例を挙げてみます。
日常生活にあるトレードオフの3つの例①財布のサイズ
最近は「クレジットカード・お札・少量の小銭」が入る、コンパクトでスタイリッシュな財布が流行っています。
しかしその財布は、多量のレシートやカード、そして小銭が発生した時には入りきらなくなりますよね。
つまり「コンパクトで携帯し易いこと」と「収納量」はトレードオフの関係にあると言えます。
日常生活にあるトレードオフの3つの例②家賃
家賃も様々な要素とトレードオフの関係にあります。
関係にあるのが「駅からの近さ、部屋の大きさ、眺めの良さ、築年数、立地条件」など。
たとえば同じマンションにおいては、一般的には部屋が大きくなればなるほど家賃は高くなりますよね。
つまり「部屋の大きさを取る」と「その分のお金失う」というトレードオフの関係になります。
日常生活にあるトレードオフの3つの例③タバコ
タバコを吸う方に理由を聞くと、「ストレスの軽減・緊張が和らぐ・皆で吸うのが楽しい」などがありました。
しかしその一方で、その人物としては「わざわざ喫煙場所を探さなければならない・衣類などにタバコ臭が付く・タバコ切れが気になる」などの、余計なストレスもあるとのこと。
これもタバコを吸う上でのトレードオフな関係でしょう。
ビジネスにおけるトレードオフの2つの例
ビジネスにおける分かりやすい「トレードオフの例」を2つ紹介します。
ビジネスにおける分かりやすいトレードオフ例①価格と品質
製品やサービスを作るときには、消費者を満足させるだけの「品質」を追い求める一方で、ライバル社に負けないために「価格」を抑える必要があります。
当然、消費者にとって価格は安い方が喜ばれますが、良い商品を安価で提供しようと思うと、企業としては利益が縮小します。
つまり「品質」と「価格」はトレードオフの関係にあると言えます。
なお、もしも「高い価格」で「低い品質」のものを売ろうと思うと、そこには付加価値を加える必要があります。
『料理は微妙(低品質)だけど、キッズスペースもあって子ども連れで来やすい!価格は安くないけど、周りを気にせず快適に過ごせるから重宝する!』
この場合も「キッズスペースに対する家賃(坪単価)」が掛かりますので、完全にトレードオフが解消しているとは言えませんが、「何かで補足する」ことで解消する可能性はあるということです。
ビジネスにおける分かりやすいトレードオフ例②需要と在庫
【需要と在庫】についても、「ビジネスにおけるトレードオフ」の例としてよく挙げられます。
「需要」がある物であれば、多くの注文に対応できるように「在庫」を多く抱えておく必要があります。
なぜなら在庫が少なければ、せっかくの「売れる機会」を逃すからですね。
かと言って、あまり多くの在庫を抱え込んでしまった場合は、
- 売れなければ仕入代金を回収できない
- 仕入代金を回収できないことで、資金は減少したままになる(資金繰りの悪化に繋がる)
- 保管する場所が必要(余計な賃貸料が掛かる)
- 棚卸に人員・時間が必要(人件費が掛かる)
という問題を引き起こします。
このような理由から、「需要」と「在庫」はトレードオフの関係にあると言えるのです。

ちなみに、ビジネスにおいては「経営課題=トレードオフの解消」というケースも多いです。
解消できた結果、ビジネスの拡大や新たなチャンスに結びつく可能性があります。
経済学における代表的な2つのトレードオフ
経済学においても、トレードオフは存在します。
経済学における代表的な2つのトレードオフ①「失業率」と「物価」
失業率と物価は、逆相関する関係にあります。(フィリップス曲線で表されるもの)
その関係性は、「物価が上がる」と「失業率は下がる」、そして「物価が下がる」と「失業率は上る」というもの。
その理論を分かりやすく言うと、以下の流れです。
「物価が上がり、失業率が下がる」流れ
- 物価が上がる
- 企業の売上UP
- 売上が上ってもすぐに従業員の賃金は上げないため、企業の利益が増える
- 積極的に雇用を増やす
- 失業率が改善する(下がる)
「物価が下がり、失業率が上る」流れ
- 物価が下がる
- 企業の売上DOWN
- 従業員の賃金を下げられないため、リストラなどを行う
- 失業率が悪化する(上る)
このような流れから、「物価」と「失業率」の関係性はトレードオフだと言えます。
経済学における代表的な2つのトレードオフ②「経済成長」と「環境破壊」
「経済の成長」と「環境保全」もトレードオフの関係にあると言われます。
たとえば、「CO2の濃度を下げなければ地球温暖化は止まらない」と言われる一方で、「経済成長には多くのエネルギーが必要となり、当然CO2の排出量も増える」とも言われます。
つまり「経済成長」を取れば「環境破壊」に繋がりますし、「環境」を守れば「経済」は衰退するというトレードオフです。

技術発展とともに「環境に優しい技術」が生まれれば、その時はこのトレードオフは解消し、「経済成長」と「環境保全」が両立されることでしょう。
一緒に語られる「機会費用」ってなに?
「トレードオフ」の解説の際に一緒に語られることの多い、「機会費用」という言葉。
これは「トレードオフにおいて、他の選択肢を選べば得られたはずの利益」のことを言います。
少し違う言い方をすると、「ある行動の選択によって失われる、他の選択を選んでいれば得られたであろう利益」のこと。
例:
高校卒業後、「大学に通う」「就職する」という選択肢があった場合…。
- 「大学に通った場合」の機会費用
⇒4年間の仕事で得られるハズだった所得、および知識・スキルなど
- 「就職した場合」の機会費用
⇒自由な時間、大学で得られる友人、大学で身に付く知識など
上記の通り、大学に通った場合は「4年間の仕事で得られるはずだった所得」が「他の選択肢を選んでいれば得られたであろう利益」であり、それはまた「大学に通うために支払った費用※」とも言えます。
※「大学に払うための学費」ではなく、大学に通うという選択に対する費用
ちなみに経済学者のクルーグマンは、機会費用のことを以下の通り述べています。
欲しいものを手に入れるときに、諦めなければならないもののことを機会費用と呼んでいる。
このように、必ずしも「費用」=「お金」ではなく、経験なども含めて「費用」と表現しています。
「ジレンマ」と「トレードオフ」は何が違うの?
ジレンマとは、相反する2つの選択肢から一つを選ばなければならず、かつどちらを選んでも不利益になりかねない状態のことを言います。
表現を変えると「望ましくない2つの選択肢のうち、どちらか一方を選ばなければならない状況に陥ること」。
一方のトレードオフとは、「何かを得たいと思った時に、一方では何か別の物を失う」という状況です。
つまりトレードオフでは「望ましいものを選ぶ時に、何かを犠牲にしなければならない」というニュアンスなので、選択肢の大前提からして異なります。
まとめ
トレードオフの意味や使われ方、機会費用や類語との違いについて解説しました。
最後に簡単にまとめます。
- トレーオフとは、簡単に言うと「何かを得る時には、何か別の物を失う」ということ
- 「お金」を得るために一日中働いた場合には「時間」を失う、というのが分かりやすい表現である
- 日常生活やビジネスシーンだけでなく、経済学においても使われる言葉である
- 「トレードオフにおいて、他の選択肢を選べば得られたはずの利益」のことを【機会費用】と呼ぶ
- ジレンマは「望ましくない2つの選択肢のうち、どちらか一方を選ばなければならない状況に陥ること」であり、選択肢の大前提から異なる